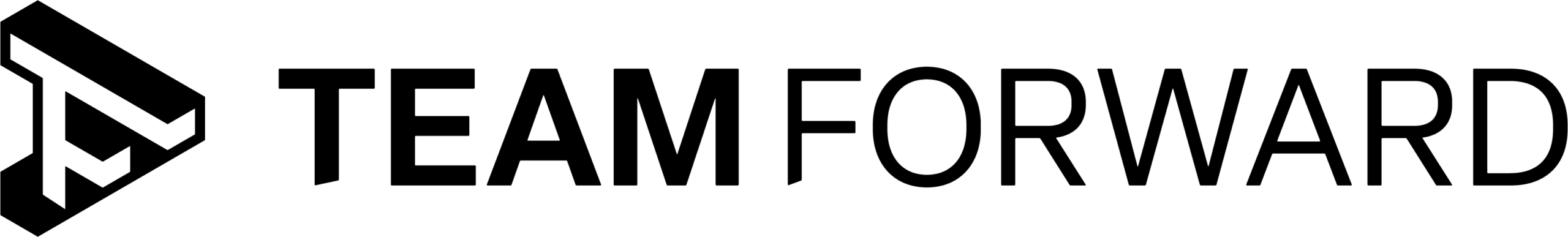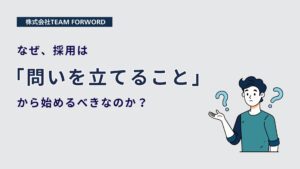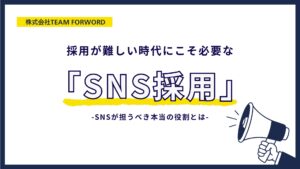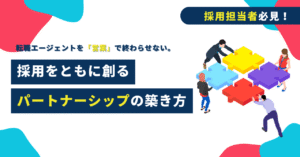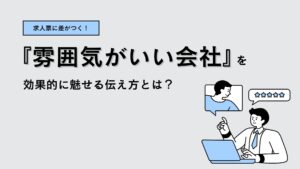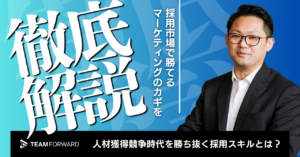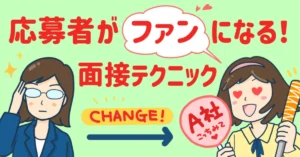なぜ研修しても成果が出ないのか?- 本当に効果のある社員研修のつくり方 –

こんにちは、TEAM FORWORDの竹田です。
弊社は、人と組織の力で企業を強くする支援をする会社です。
その一環として、人材育成領域にも力を入れており、その手法のひとつが社員研修です。
今回は、これまでさまざまな企業の社員研修を行ってきたTEAM FORWORDが、
「本当に効果のある社員研修」を実現するためにおさえておくべきポイントについてお話しします。
【目次】
1.効果が出るのは、「良い研修」より「合う研修」
2.研修の成果を決めるのは「何を教えるか」だけでなく「誰が伝えるか」
3.研修の成功は「前後の設計」で決まる
4.まとめ
それでは早速、本題に入っていきましょう!
1.効果が出るのは、「良い研修」より「合う研修」
社員研修には、目的や対象によってさまざまな種類がありますが、大きく分けると以下の2つに分類されます。
① 技術研修
製造現場で行われる機械操作などの技能実習、販売職での商品知識や接客トークの習得など、
実務に直結する「専門スキル」を身につけるための研修です。
内容は、仕事で必要とされる「技術・知識・手順」を反復的に学ぶのが特徴で、
講師は主に社内の上司や、製品・サービスに詳しいメーカー担当者など、
実務経験と専門知識を持つ人が担当します。
② ビジネススキル研修
一方で、どの業種・職種にも共通して求められる汎用スキルを磨くのが、ビジネススキル研修です。
コミュニケーション、リーダーシップ、チームマネジメント、問題解決力など、
あらゆる職場で必要とされるスキルを扱います。
講師は、これらのスキル開発を専門にした研修講師やトレーナーが担当。
TEAM FORWARDが実施しているのはこちらの研修です。
本日は、「ビジネススキル研修」についてお伝えします。
ビジネススキル研修のご相談を多数いただく中で強く感じるのは、
「目に見えている問題」と「本当に解決すべき課題」は必ずしもイコールではないということです。
たとえば、「若手社員が主体性を持てない」というよくある相談。
経営者や人事担当者視点では、これが解決したい問題です。
しかし、若手社員に話を聞くと、
「意見を言っても最終的に上司が決めるから意味がないんです」
という声が出てくることがあります。
この場合、問題の真因は「若手の意識」ではなく、「主体性を発揮できない環境そのもの」なのです。
任される場がなければ、主体性を発揮できないのは当然のことです。
実は、必要なのは若手向けの研修ではなく、上司が意見を引き出しやすい場をつくるための
マネジメント研修やコミュニケーションの見直しかもしれません。
このように、目に見える問題だけに対して「対処療法的」に研修を行っても、
本当の課題には届きません。
根本的な改善につなげるには、「何を教えるか」よりも「なぜそれを教えるのか」を明確にし、
課題の本質にアプローチできる研修を設計することが大切です。
「最近流行っている研修って何ですか?」「他社ではどんな研修をやっていますか?」
と聞かれることもよくありますが、どんなに人気の研修でも、
その会社の課題に合っていなければ意味がありません。
他社と同じメニューを取り入れても、同じ効果が出るとは限らないのです。
本当に良い研修とは、自社の課題を正確にとらえ、その課題を解決できるコンテンツを、
適切な講師が届けられることだと考えています。
言い換えれば、「良い研修」は企業の数だけ存在するということです。
だからこそ、まずは問題の真因をしっかり見つめ直すことが、効果的な研修づくりの第一歩になります。
TEAM FORWARDは、課題を正確に掴むことに丁寧に時間を掛け、オーダーメイドの「合う研修」を提供することを心掛けています。
2.研修の成果を決めるのは「何を教えるか」だけでなく「誰が伝えるか」
研修の方向性(=問題の真因)を正しく捉えたうえで、
次に重要になるのが「誰が、どのように伝えるか」という視点です。
同じテーマでも、講師や伝え方によって受講者の理解度や現場での活かされ方は大きく変わります。
ここで押さえておきたいのが、講師にもさまざまなタイプがあるという点です。
理路整然と、かつ、分かりやすく伝える、先生タイプの講師もいれば、
敢えて雑談も交え、一体感の中で耳を傾けてもらうスタンスの講師もいます。
つまり、講師のスタイルと受講者・組織文化との「相性」があるということです。
この相性が合えば学びは深まり、研修効果も大きくなりますが、
逆に噛み合わないと「意味がなかった」と感じてしまうこともあります。
社風・受講対象者・研修実施背景などによって「誰が教えるか」もしっかり検討したいところです。
多くの企業が「研修をやっても変わらない」「効果が見えない」と感じる背景には、
研修自体の価値がないのではなく、相性や目的の設計が十分に考えられていないという現実があります。
研修は「やること」自体が目的ではありません。
人が変わるきっかけをつくり、組織が前に進むための仕組みです。
「どんな人が、どんな伝え方で、誰に届けるのか」を意識して設計することで、
研修の成果は大きく変わっていきます。
3.研修の成功は「前後の設計」で決まる
ここまで「いい研修とは何か」についてお伝えしてきましたが、
実は効果を大きく左右するのは研修内容そのものだけでなく、その前後の取り組みです。
2007年にウエストミシガン大学のロバート・ブリンカーホフ教授が発表した研究では、
研修効果を分析した「4:2:4の法則」が紹介されています。
「4:2:4の法則」:効果のない研修プログラムの原因
・受講者の事前準備・環境整備の不足:40%
・研修内容自体の問題:20%
・研修内容実施に対する環境上の障害:40%
(出典:マイナビ HR Trend Lab/研修前後の取り組みも重要!研修効果を高めるための5つのポイント)
この法則によると、研修効果が上がらない原因のうち、約4割は「事前準備の不足にある」とされています。
つまり、研修の内容だけでなく、研修前の環境づくりや研修後のフォローがあってこそ効果を最大化することができるのです。
では、具体的にどんな工夫をすれば「効果の出る研修」になるのか。
ここからは、研修の「前」「後」のフェーズに分けて、意識すべきポイントを具体的に見ていきます。
研修前:関心と目的意識を共有する
たとえば、上司が部下の研修日程や内容を把握していないと、
受講者は「自分の成長に会社は関心がないのかも」と感じてしまいます。
それだけでも研修自体の意義が薄れてしまい、学びへの意欲は大きく下がってしまうのです。
効果的な研修にするためには、
「研修の目的と期待を明確に伝えるメッセージ」を事前に発信することが重要です。
「今、会社が目指している方向」や「今回の研修がそのために必要な理由」を伝え、
社員に「なぜこの研修を受けるのか?」を理解してもらえるようにしたり、
研修当日の冒頭で社長講話や役員講話を設け、
「この一日を成果につなげてほしい」と直接言葉で伝えることも有効です。
特に、「会社としてこの研修にどれだけ価値を置いているか」が伝わると、「やらされている研修」ではなく、「会社の未来を担うための大切な時間」として受け止めるようになります。
研修後:定着のカギは「アウトプットの場づくり」
研修が終わったあとに効果を左右するのは、
職場でのフォローや学びをアウトプットする機会です。
人は学んだ内容の約75%を1か月後には忘れるといわれています
(ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスによる「忘却曲線」より)。
だからこそ、やりっぱなしにせず、学びを言語化・共有する場を設けることが大切です。
研修後に立てた目標や気づきを振り返り、チーム内で「研修でこんなことを学んだ」「こういう行動を意識してみたい」と話し合ってみたり、あるいは上司が「研修で言ってたあれ、実践できそう?」と声をかけたり面談を実施してみたり。
そうした日常的なやり取りが、受講者の記憶を呼び戻し、行動の定着へとつながります。
また、コミュニケーション系の研修であれば、社内で定期的にロープレを実施したり、成功事例を共有する場を設けたりするのも効果的です。「そういえば研修でこんな話をしたよね」と思い出すきっかけをつくることで、
「学びを定着させる文化」を育てていくことができます。
最後に:学びを行動に変えるのは、現場の一人ひとり
どんなに研修前の準備や研修後のフォローに力を入れても、
現場でそれを実践する人たちが行動できていなければ、成果にはつながりません。
たとえば、研修で「後輩の話をしっかり聞く姿勢が大切」と学んでも、
日常で上司がパソコンを打ちながら話を聞いていたら、
「結局やらなくていいんだな」と部下は感じてしまいます。
課題の主因を丁寧にたどっていくと、研修の内容だけでなく「誰を対象にするか」も変わってくるのです。
本当に効果のある研修をつくるためにも、研修内容だけではなく「前後の設計」「対象者の設計」もぜひセットで考えてみてください。
4. まとめ
社員研修は「一日の学び」で終わるものではなく、課題を正しく捉え(設計)・現場で実践され(実行)・行動として根づく(定着)ことで、初めて効果を発揮します。
そのためには、
- 自社の課題に合った内容を見極めること
- 現場の文化や受講者に合った講師・スタイルを選ぶこと
- そして研修前後を通じて、学びを支える環境を整えること
この3つのバランスが欠かせません。
どれか一つでも欠けると、どんなに優れたプログラムでも成果は限定的になってしまいます。
だからこそ、「何を教えるか」ではなく、「誰に・どのように届け、どう定着させるか」を軸に、
自社らしい研修設計を考えることがとても重要になるのです。
TEAM FORWORDは、企業ごとの課題や組織のステージに合わせて、
「人と組織の力」を最大限に引き出す研修づくりをサポートしています。
もし自社の育成体制を見直したい、研修の効果を高めたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。