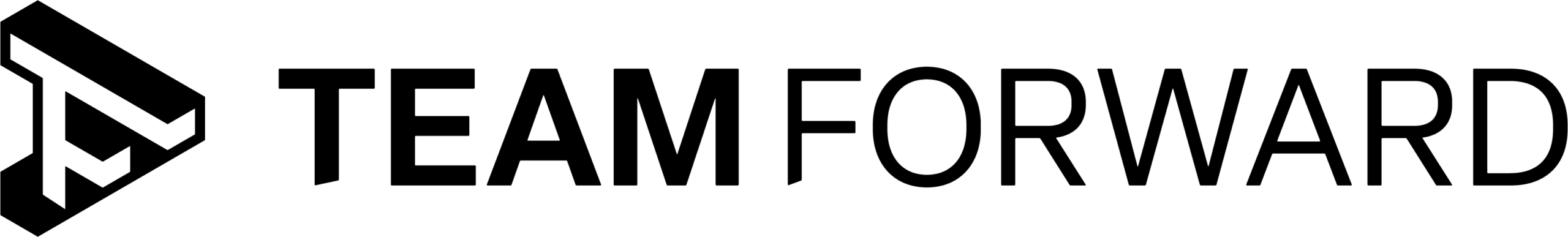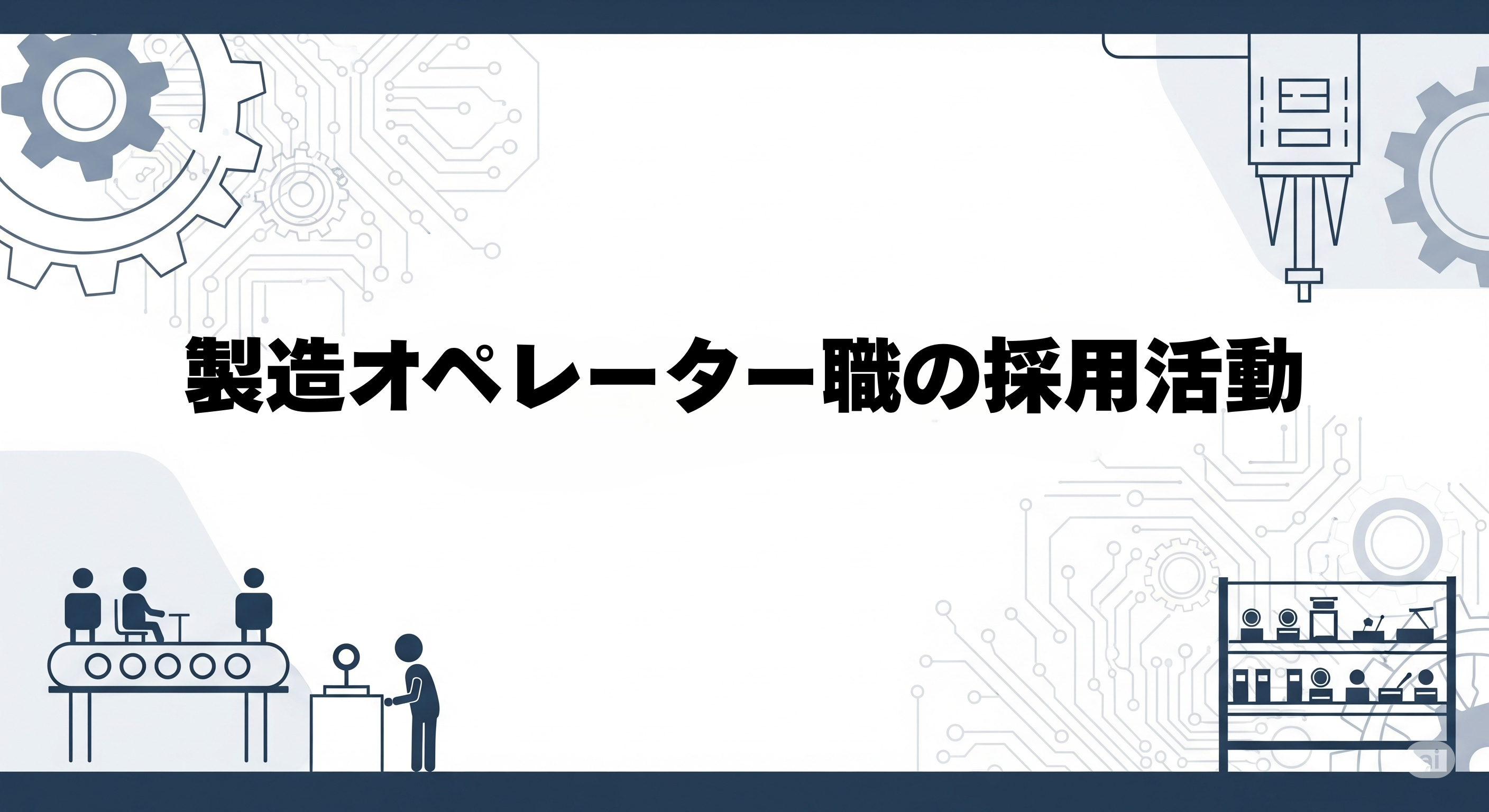「法人営業職」の採用活動・求人
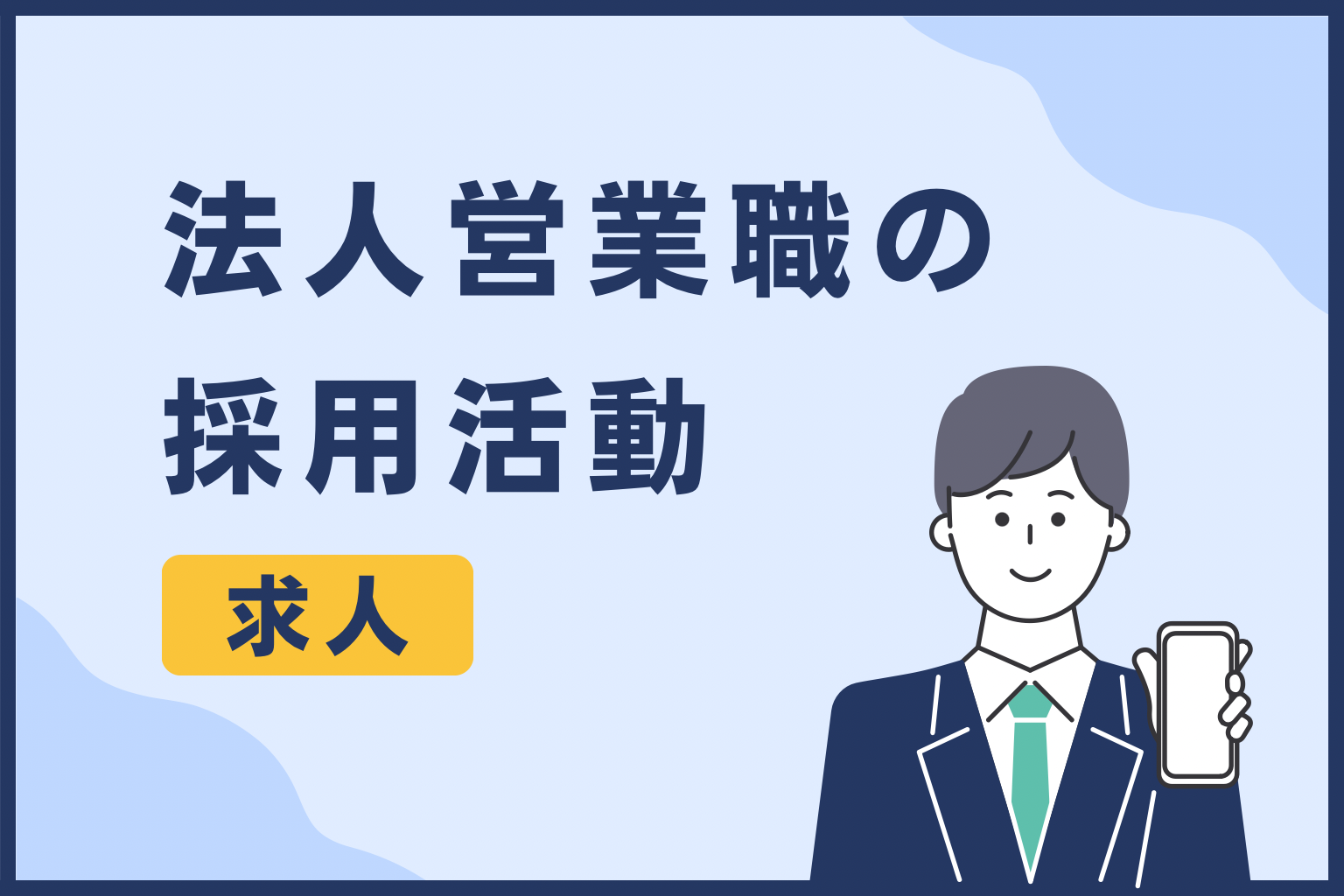
法人営業職の採用活動・求人における傾向や押さえておきたいポイントと、チームフォワードにできる採用支援をご紹介します。
法人営業職の採用活動に関して、こんなお悩みありませんか?

若手からの応募が来ない…



面接前の辞退者や連絡が取れなくなる人が多い…



能力の見極め方が分からない…
採用活動を“点”ではなく“線”で捉えて勝ち筋を見つけることで、採用課題を解決します。
法人営業職の採用・求人に関する傾向・特性
若手からの応募が来ない
前提として、現代は人口減少社会となっており、そもそも若者の数が以前よりも少ない状況です。さらに、色々なものがweb化し、AIも普及したことで、webに関する仕事(webデザイン・マーケティング・動画編集/映像クリエイター・SNS運用など)に人気が集まるようになりました。
つまり、営業・販売・事務などといった従来型の職種だけでなく、
未経験からでも多様な職種に挑戦できる時代になった、という大きな変化が起きています。
このような変化の中で、あえて営業職を志望するという若手が減少していると考えられます。
面接前の辞退者や連絡が取れなくなる人が多い
色々なケースはありますが、これまでの傾向と大きく違う点がひとつあります。
それは、今の若手にとっての応募は、いわゆる「ブックマーク」のような感覚であるということです。
以前は、1社に応募するために志望動機を練り上げ、企業研究を徹底し、面接対策も万全にしたうえでようやく応募する、というのが一般的でした。現在は、複数の求人に対してまずエントリーをし、書類選考を通過した段階で初めて企業研究や準備を本格的に始める、といったスタイルが主流になりつつあります。
しかし、いざ調べようと思ったときに、企業ホームページが何年も更新されていなかったり、知りたい情報が得られなかったりすると、「どういう会社なのか分からない」と感じてしまい、志望動機がうまく作れないことで辞退に繋がってしまうケースも少なくありません。



企業側の発信力こそが志望動機を形成させ、辞退を防ぐ最大の鍵になります。
能力の見極め方が分からない
営業職経験者の経歴は、MVPの受賞、高い目標達成率といった「数字」で華やかに見えることが少なくありません。しかし、その実績だけでは本当の実力を見極めることは難しいのが実情です。
例えば、5年間で2回月間MVPを受賞していたとしても、それ以外の58カ月の成果はどうだったのか?は分かりません。また、案件引継ぎなどの外部要因で、本人の実力以上の数字が出ている可能性もあります。
また、もう一つ注目したいのは、会社によって営業目標設定の考え方が異なる点です。
A社では社員の大半が目標達成をしている一方で、B社では達成者が2割程度しかいないといったケースでは、同じ「100%達成」という数字であっても、その意味合いは大きく変わってきます。
つまり、営業経験者の能力を判断する際には、単なる数字や表面的な実績だけでなく、その背景や環境を踏まえて見極める必要があるのです。
課題発見から解決のためのアプローチ
Point1.募集年齢層の理由を明確にする
「若手を採りたい」で思考停止せず、なぜその年齢でなければならないのか?を明確に言語化します。
営業職においては、40~50代の経験者は、立ち上がりの速さや既存ネットワークを武器に、短期で売上を作れるケースも少なくありません。定年を65歳とすれば、50歳入社でも残り15年の貢献余地があります。
一方、平均年齢50代の職場に20代を単独投入すると、馴染むのに時間がかかったり、戦力化するまでに負荷がかかる=いわゆるオンボーディングが難しくなり、早期離職リスクが高まることもあります。
年齢も目的ではなく手段。固定観念を一度外し、事業にとって最適なバランスを設計することが出発点です。もちろん、その上でも若手採用が必要であれば、腰を据えた戦略設計が必要になります。



「若手を採る」を一度棚卸しし、どんな成果を・どれくらいの期間で・どんな体制で実現したいかまで落とし込むことが大切です。
Point2.オウンドメディアの活用と採用ブランディングの見直し
これまで転職活動は「現職 → 退職 → 次の就職」と、明確に気持ちを切り替えて行うのが一般的でした。
しかし現在は、働きながらも良い会社があればいつでも動けるように、常にゆるやかに転職活動を並行している人が増えています。現職という船に乗りながら、横を走っている船にいつでも飛び移れる準備をしている、というイメージです。しかし、現職という船でも前に進んではいるので、自分にとってより良い船であると思わなければ、何もアクションを起こさない。これが、「転職活動者はたくさんいるにも関わらず、自社には全然応募が来ない」というギャップの理由です。
就職活動をしている学生に、知っている企業名を挙げさせたら、何社挙がるでしょうか。誰もが知る世界的企業と、地元大手が数社といったところではないでしょうか。就職・転職活動をする人にとって、99%以上の会社は”初めて名前を聞いた会社”といっても過言ではありません。
古いホームページや情報発信のない企業は「よく分からない会社」として埋もれてしまいがちです。
一方で、SNSやブログなどを通じて、社内の雰囲気や経営者の考え方を発信している企業は、候補者に具体的なイメージを持たせ「この会社面白そう」と思わせるきっかけを作ることができます。小さなことからでも構いませんので、自社を知ってもらうアクションを”まず始めてみる”ことをしてみてはいかがでしょうか。
ここで明確に否定しておきたいのは、”良い会社に見せる”ことが目的ではなく”どういう会社か分かる”ことが大切であるということ。もちろん、常識の範囲内で見せ方を整えることは必要ですが、、
人々を情報を見る目が肥えている昨今では、誇張が過ぎれば「怪しい」「そんなに良いことばかりなはずがない」と逆にネガティブな印象に繋がる可能性もありますので注意しましょう。
Point3.コアスキルを言語化し、数字を相対的に捉える
営業経験者を採用する際に重要なのは、「売れる人はなぜ売れているのか」を自社の基準で言語化することです。
例えば「愛されキャラ」「論理的に話せる」「大手向き/中小向きには強い」など、営業が成果を生む要因は商材や顧客などによっても異なります。貴社で成果を出している人の特徴を分析し、そこから面接で見極めたい要素を明確にしていきましょう。
また、数字を相対的に判断する視点も欠かせません。
同じ「100%達成」という実績であっても、達成率が社員の大半にとって当たり前の環境と、達成者が2割しかいない厳しい環境とでは、その価値は大きく異なります。例えば「周囲の平均が60~70%の中で自分だけが100%を達成した」といったケースであれば、その人は強い目的意識や工夫を持って成果を出している可能性が高いといえます。そうした背景を掘り下げる質問をすることで、候補者の思考や行動特性を把握することができます。
チームフォワードにできること
1.オウンドメディアの構築・運用
私たちは採用支援の専門家として、採用成果につながるオウンドメディアの構築・運用を一貫してサポートします。単に見栄えの良いホームページをつくるのではなく、採用の知見に基づき、求職者の行動プロセスに沿った訴求導線を設計することが特徴です。
「どうすれば求職者に選ばれるか」を理解している私たちにお任せいただくことで、単なる情報発信にとどまらない、成果につながる採用ブランディングを実現できます。


2.選考プロセス設計
現在の選考プロセスを確認しながら、これまで採用してきた方がなぜ採用に至ったのかを明確にします。
併せて、どのような人を採用したいのか?を丁寧にヒアリングし、オリジナルの最適な採用基準を選定します。
また、面接にも同席し、実際に選定した採用基準での面接のやり方や採用フローを見直します。
選考プロセスを再設計することで、「魅力の伝達」と「見極め」の両立を実現することができます。
3.戦略を確実に実行するアウトプット(求人広告・求人票ディレクション)
立派な戦略を描いても、アウトプットされる求人広告や求人票のクオリティが低ければ、戦略は実行されなかったのと同じです。
求人が溢れている昨今、「どの会社も似たようなことを言っている」「どうせ良いことしか書いていない」という見られ方をしているのが現実。その上で、他の会社とは何か違う、この会社の言っていることは信用できそうだ、と感じてもらう為には、文章や写真、求人票閲覧前後のアクションも含め、文脈が一貫していることが大切です。
当たり障りの無い求人票ではなく、他との違いが分かる求人票を作成します。求人広告をご掲載頂く場合、ディレクション費用は無料です。これまでに使用されている求人広告と同額でご利用いただけます。